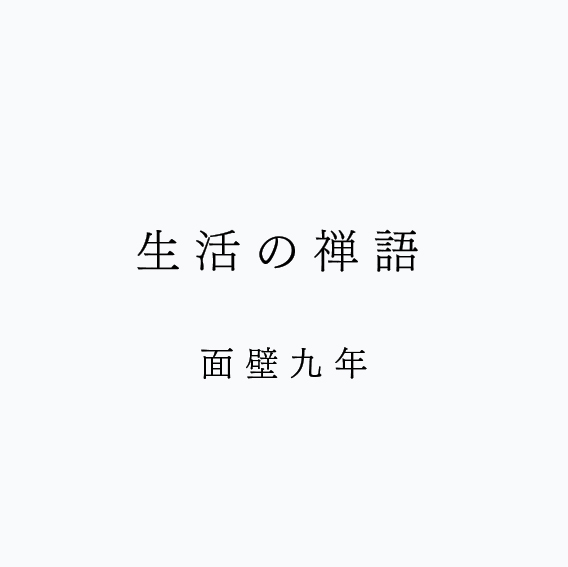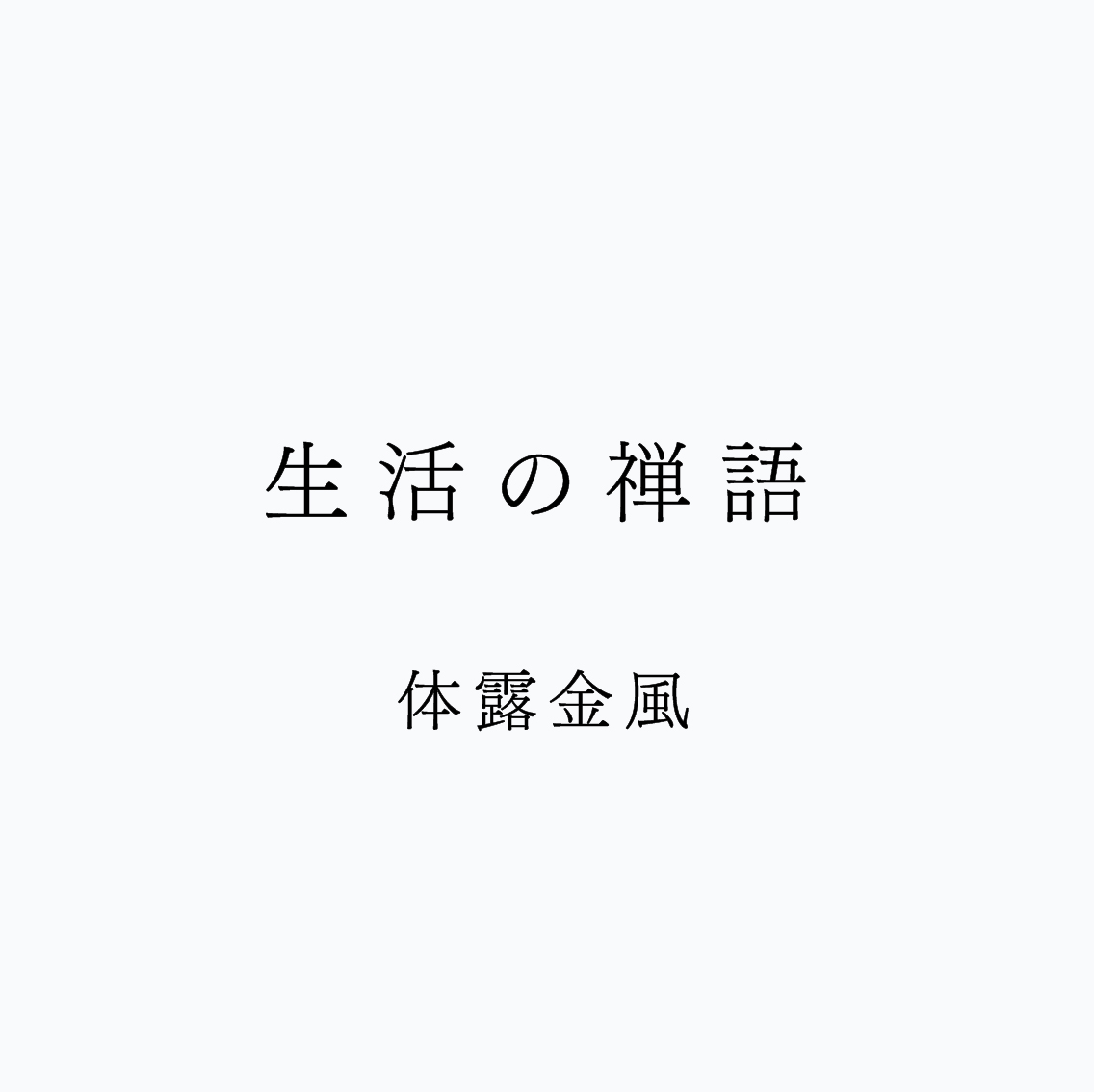2025.4.30
西芳寺の地霊(前編)
造園学者 尼﨑博正
土地に刻まれた歴史を呼び起こす
ゲニウス・ロキとは、ラテン語で地霊、場所の精霊を意味します。西芳寺の長い歴史を振り返り「土地の記憶」と向き合うとき、その存在を確かに感じることでしょう。
西芳寺では、開山1300年を記念して水路の復元事業に取り組んでいます。2025年2月に、事業の委員長である尼﨑先生に「時間の多層」をテーマに講演していただきましたので、その内容を記事にしてお届けします。西芳寺の歴史を掘り下げるお話となりますので、歴史の概略を知りたい方は「波乱と悠久の歴史」をご覧ください。
尼﨑 博正(あまさき ひろまさ)
造園学者、作庭家、京都芸術大学名誉教授、日本庭園・歴史遺産研究センター名誉所長。1946年生まれ。京都大学農学部を卒業後、京都市内の造園業者に弟子入りし、さまざまな現場で経験を積んだのち独立。同時に長きにわたり、多くの学生に造園の歴史・文化や作庭について教えるとともに、専門家として全国で文化財庭園の保存修復を指導。1992年に日本造園学会賞を受賞、2014年には京都市文化功労者として表彰される。

お庭造りと修行は同じ
今日は「時間の多層」をテーマにお話します。西芳寺の中興開山の祖であり、今の庭園の原型をつくった夢窓国師の庭造りから、西芳寺庭園の時間の重なりを解き明かしてみたいと思います。
西芳寺のお庭は、自然への洞察や共感が、ひしひしと感じられる空間だと思っています。夢窓国師は自然への共感を大事にしていたと同時に、庭園史的には新しい時代を切り開いた人である、というのが私の庭園史家としての見解です。

夢窓国師に関する文献の一つに、『夢中問答集』というものがあります。これは、夢窓国師が足利直義からの問いに答えた法話集です。足利直義は、初代室町幕府の将軍・足利尊氏の弟ですね。この本には仏道に関する様々な問答が記されていますが、庭作りのことにも触れられています。
「山河大地、草木瓦石、皆これ自己の本分なりと信じる人……道人の山水を愛する模様(手本)としぬべし……山水には得失なし。得失は人の心にあり。」
(『夢中問答集』五十七段(校注:川瀬一馬、底本:康永3年(1344)刊の五山版)
「山水」とは山水を模した日本庭園のこと、「得失」とは利益と損失のことです。つまり、山水庭園に損得はないのだから、それを好むことは良いこととも悪いこととも言えない、損得はそれを見る人の心の中にあって、見る人の捉え方によって変わってくるのだと言っているんです。
また、こうも書いてあります。お庭に興味があるという人には色々な人がいて、珍品を集める人もいれば、白楽天のように趣を楽しむ人もいる。けれども基本は、お庭造りと修行というのは一緒なんだ、と。これが最も重要だと思います。山河大地、草木瓦石、ありとあらゆるもの全て皆自己の本分であると信ずる人が求道者の本当の姿であって、山水と仏道の修行とを別ものと考えていては、十分ではないんだと。求道者が山水を愛する、それを模範としましょうと、そう言っているんですね。
自然を自分なりに造形する時代へ

ここで、お庭の造形についてお話をします。平安時代の庭園において最も重要な意匠的特徴といえば、州浜です。庭園内の池や水の流れを海や河に見立てるときに、岸辺の表現として石を敷き並べます。宇治の平等院が代表的ですが、池の際に石を敷き詰めることで、非常におおらかで爽やかな景色を作り出しています。海の風景を基本にした、自然に倣った庭づくりでした。
これに対し、夢窓国師は石組みによる立体的で力強い造形を導入します。
それまでの庭園にも石組みはありましたが、あくまで部分的に用いられるだけでした。それを夢窓国師は、あらゆる山水の姿を表現するために、石組みを用いるんです。私はこれを風景の再構成と言っていますが、彼は、自分なりの心象風景を作っていくわけです。
これはもう非常に革命的なことだったはずです。だから私の歴史観としては、夢窓国師によって、庭園は自然を自分なりに造形する時代へと突入していったと考えています。
西芳寺庭園の革新的な空間づくり

では、西芳寺庭園はどのような造形がなされたのでしょうか。
まず、上段の庭の枯山水庭園(※通常非公開)。これは枯山水としては最初のものだと私は考えています。枯山水という言葉自体は、平安時代からあります。池も遣水もないところに石組みをつくることを、枯山水と呼んでいました。しかしこれは庭園の一部の要素に過ぎません。それを夢窓国師は一つの庭園様式としてズームアップしたわけです。
また、枯山水庭園からさらに山を登ったところには、縮遠亭という建物がありました。現存していませんが、比叡山をはじめ、京都一帯が見渡せるほどの素晴らしい眺望地点だったようです。
夢窓国師が作庭したお庭の一つに鎌倉の瑞泉寺がありますが、このお寺にも徧界一覧亭という亭が建てられていました。今は非公開となっていますが、この眺望地点からは富士山が見えます。夢窓国師は、眺望を大変重要視されていたということです。

下段の庭に移りますと、方丈には「富士の間」という部屋がありました。その部屋からは比叡山が見えるので、比叡山を富士山に見立てているんですね。富士山信仰が広く認識されていたことの大きな証だと思います。
また、瑠璃殿という二層の建物もありました。金閣寺や銀閣寺にも二層の建物がありますが、これは西芳寺の瑠璃殿を模して作られたと言われています。高さのある建物で視点を上にあげて、庭園を見る。こうした立体的な空間デザインを初めて持ち込んだのが西芳寺でした。
自然と融合した、心のふるさとのような存在
ところで、夢窓国師は同時期に嵐山の天龍寺の庭園も造っています。この天龍寺庭園は、西芳寺とはまた違った特徴を持っています。
何が違うのかというと、石です。
少し京都の地形のお話をしますと、2億数千万年ほど前、京都は海の底でした。その海の底の堆積岩が隆起していって、今の京都盆地が作られていきます。ですので京都の山は堆積岩で作られていることになるわけですが、この堆積岩は、砂が固まった砂岩、泥が固まった頁岩、それからプランクトンが固まったチャートという、大体3つの石でできています。西芳寺の周辺の山はほとんどが砂岩で、天龍寺のあたりは頁岩でできています。
基本的に庭園を造るときは近所の石を使いますので、西芳寺では砂岩が主に使われています。ところが天龍寺庭園の滝石組みには、結晶片岩という、京都では取れない石を使っているんです。おそらく和歌山辺りから運んできた石だと思います。

天龍寺は後醍醐天皇の菩提を弔うために建てられた、いわば公のもので、石も和歌山から取り寄せています。一方の西芳寺では、地元の石を使って、地元の環境の中で庭造りをして、真に自然と融合した空間を作っています。そうした石の違いを見ると、夢窓国師にとって、西芳寺は心のふるさとだったのではないか、そんな想像ができるんです。
後編では、当時の西芳寺が人々にとってどのような存在であったのか、そして時を経て現在行われている水路復元事業の意義について考えていきます。後編はこちら>>
編集:宮内 俊樹
執筆:細谷 夏菜
写真:into Saihoji編集部
※許可を得て撮影しています。