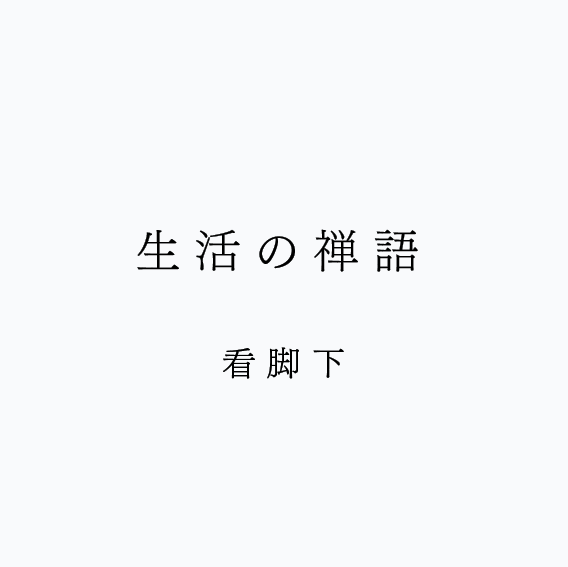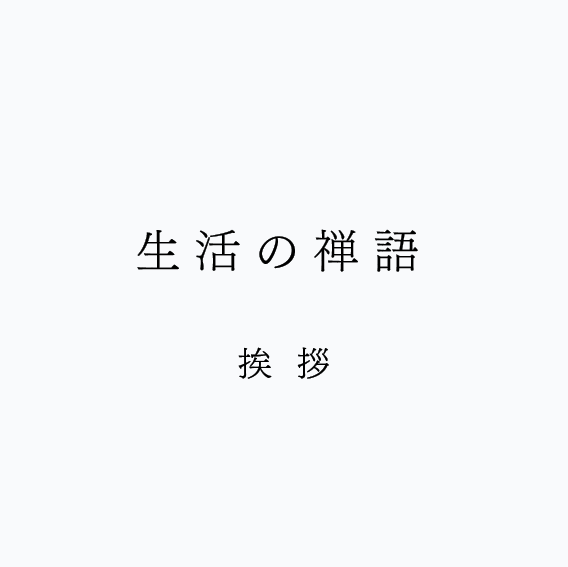2025.9.15
生活の禅語 「無功徳」
禅語「無功徳」の元になっているのは、これまでもご紹介してきた禅の書物『碧巌録』の第一則にある、次のやり取りです。
達磨、初めて武帝に見えしとき、帝問う、朕、寺を起て僧を度す。何の功徳か有る。磨云く、功徳無し。
これは中国の南北朝時代(439~589年)に、梁の武帝と達磨大師との間で交わされた問答です。
武帝は、仏教に深い信仰心を持ち、仏心天子とも称された人物です。即位以来、数多くの寺を建立し、多くの人々を出家させるなど、仏教の興隆に尽力してきました。
達磨大師は、西芳寺の朱印でも書かせていただいていますが、始祖であるお釈迦様から数えて28人目の祖(西天二十八祖)であり、かつ禅宗の開祖でもある、偉大な祖師でいらっしゃいます。「だるま落とし」もこの達磨大師に由来し、親しみやすいイメージをお持ちの方も多いと思います。
武帝は達磨大師を宮中に招き、こう尋ねます。
「私はこれまで寺を造り、僧侶を供養してきました。私にはどのような功徳があるでしょうか」
これに対する達磨大師のお答えが、「無功徳」。
つまり、「何のご利益もありません」と断じたのです。
武帝が仏事を積み重ねてきたことは、確かにすばらしい行為かもしれません。ですが達磨大師は、善根(良い行い)に見える行動であっても、そこに見返りを期待する心があっては真の善根ではないと、諭したのです。
人はどうしても、何か行動をしたらその成果や効果がはっきり現れると思いがちです。「コスパ」や「タイパ」という言葉が出てきたように、行いそのものよりも効率性だけを重視する風潮が、近年一層強まっているのではないでしょうか。
しかし、見返りを期待した打算的な行為ではなく、純粋な人間性の発露ゆえの行為こそが仏の慈悲と言えます。
もう少し具体的に説明してみますと、私たちは何か良いことをしたら、それを誰かに知ってもらいたい、認められたい、ご褒美が欲しいと、つい期待してしまいます。「なぜ私の頑張りを理解してくれないのか?」「いいことをしたら自分にもいいことが返ってこないと損ではないか?」などと思ってしまうのは良い例です。
しかし、見返りを求めてする親切は、本当の優しさなのでしょうか。
相手のためを思って何かをして、相手が素直に喜ぶ。そして相手の喜び自体を素直に嬉しいと思える心が大切であり、本当の優しさということです。
功利的な行為や打算的な行為から離れて、純粋な人間性の発露を追い求めていくのもまた仏の心であります。一朝一夕で体得することは難しいのですが、そういう世界があることを知ることが大切です。
そして、まずは自分から相手を思いやり、行動してみること。そうすれば、相手もまた誰かに優しく接しようと心掛けるかもしれません。こうして、真の優しさが人から人へと広がっていく。そんな恩送りの世界が、いま求められています。
合掌
洪隠山西芳寺 藤田隆浩